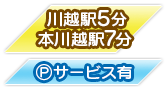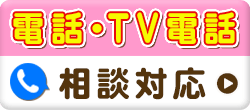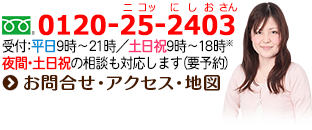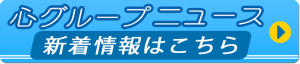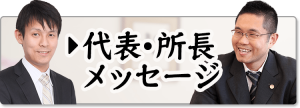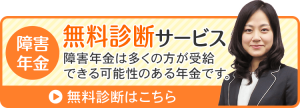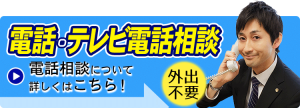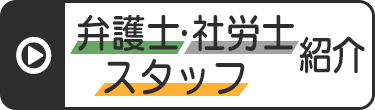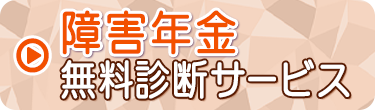初診日の第三者証明とは
1 第三者証明とは何か
障害年金の申請では、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日)がいつであるかを証明することが重要なポイントですが、初診の医療機関が廃業している、もしくはカルテを保管しておらず、その他に初診日を証明できる具体的な資料がない場合に、申請者以外の第三者の証言によって初診日が認められる場合があります。
それが第三者証明です。
2 第三者証明の提出を検討する場合
初診日の証明は、通常、受診状況等証明書という書類を初診の医療機関に作成してもらうことで行いますが、初診の医療機関が廃業している、またはカルテを保管しておらず、受診状況等証明書を作成してもらえない場合があります。
そのような場合、以下のような資料で初診日を証明することが考えられます。
・初診の医療機関から2番目の医療機関に出された紹介状
・2番目以降に行った医療機関の問診等の際に、初診の医療機関を初めて受診した時期を伝えており、その内容がカルテに記録されている場合、その2番目以降に行った医療機関に作成してもらった受診状況等証明書(ただし、そのカルテの日付が申請日より5年以上前の場合に限る)
・初診日の日付が入った診察券
・初診の医療機関の領収書
・お薬手帳
・障害者手帳等を申請した際の診断書
・生命保険金を請求した際の診断書
初診日を証明するための資料は上記以外にも色々と考えられますが、そのような資料が全くない場合は初診日の証明ができませんし、あったとしても、特に診察券や領収書等の場合には、障害年金を申請する障害と因果関係がある症状で受診したことが分からなければ、初診日であると認めてもらうのは困難です。
そこで、第三者証明の提出を検討することになります。
3 第三者証明で初診日が認められる場合
平成27年9月28日付け厚生労働省通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(いわゆる「初診日通知」)には、第三者証明で初診日を認めることができる場合について記載されています。
それによると、障害年金の申請をする本人の三親等以内の親族が行う第三者証明は認められません。
また、第三者証明は原則として2通以上必要であり、さらに第三者証明の内容と整合する参考資料の提出も必要となります。
初診日通知からは、この参考資料がどのようなものであればよいかははっきりしませんが、当法人では、診療科の特定できない初診時の領収書を提出して、初診日が認められた事例があります。
例外として、初診時に直接かかわっていた医療従事者が第三者証明を行う場合と、初診日が20歳未満である場合には、参考となる資料がなくても初診日を認めることができるとされています。
また、初診時に直接かかわっていた医療従事者が第三者証明を行う場合には、第三者証明は1通で構いません。
4 第三者証明の内容
第三者証明に記載するのは、直接見て知った初診時の状況か、本人や家族から聞いて間接的に知った初診時の状況です。
本人や家族から聞いて間接的に知った場合には、聞いたのが、障害年金の申請をする時からおおむね5年以上前である必要があります。
当然のことながら、第三者証明には、見聞きした状況をできる限り具体的に記載する必要があり、受診した医療機関名、どのような症状で受診したか、受診した時期は重要です。
特に受診した時期については、「〇〇があったから平成〇年〇月頃だ」といえるような事情を記載できれば説得力が増します。
5 第三者証明について相談したい場合
上記のとおり、第三者証明は初診日を証明するためのいわば最終手段であり、難易度が高いことから、記載する内容や提出する参考資料はよく吟味する必要があります。
当法人では第三者証明を含む様々な初診日の証明方法を実践した経験がありますので、第三者証明での初診日の証明を検討しておられる場合は、当法人にご相談ください。